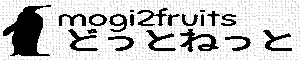SolydX – 日本語化も難しい設定も不要。そのまま使えるLinuxMintの派生OS(比較的軽量)

公式サイト:SolydX | SolydXK
日本語情報サイト:SolydX / SolydK 日本語情報サイト – SolydXKjp
このOSの概要は上の日本語情報サイトをご覧いただければ分かります(手抜き)。
カンタンに説明すると数あるLinuxディストリビューションの中でも人気の高い Linux Mint(日本語公式サイト)の派生ディストリビューションで、デスクトップ環境にXfceを採用したものが SolydX、KDEを採用したものが SolydK になります。
XfceはUbuntuやLinux Mintで採用されているGNOME・・・の中でもUnityとかMATEとかCinnamonとか色々あるのですが、それに比べて軽量です。KDEは概ね見栄えや機能は優れているけど重いです。
このブログでは主に軽量Linuxについて紹介しているので、ここではSolydXについて解説していきます。
システム要件
SolydX / SolydK 日本語情報サイト – SolydXKjpさんから引用させていただきます。
SolydX / SolydK のスペック要件
日本語環境で快適に使う前提だと、下記のスペックは必要です。
- プロセッサ: x86 32・64 ビット (PAE 非対応でも起動可能)
- メモリ: SolydX 1GB / SolydK 2GB
- ディスク空容量: 7GB (20GB 推奨)
- グラフィック: 1024×768 / SolydK 3D アクセラレータ対応
- DVD ドライブ / USB
Linux Mint Debian Edition に近いスペックとなります。
常に最新版の状態にするローリングリリースモデルのため、
このスペックは変化する可能性があります。Windows からの移行を考えている人は次の基準となります。
- SolydX: Windows XP (全バージョン)、Vista・7 (Starter/Home Basic)
- SolydK: Windows Vista・7 (Home Premium/Business/Ultimate)
ただし特に Windows XP の古い環境では、インストール後は正常でも
アップデートを行った後、急に動作がおかしくなる可能性があります。
Windows ベースでの主なターゲットは Windows Vista・7 になってくるでしょう。
なのでXP難民の救世主とは言い難いですが、Ubuntuベースの利点である「汎用性(ハード・ソフト)」はもちろん、外観や操作性も良くできているので、Linuxに不慣れな方でも扱いやすいと思います。
インストール方法
大まかな流れは以下のようになります。
イメージファイル(.iso)のダウンロード

公式サイトからイメージファイル(.iso)をダウンロードします。最新版(201407)は日本語に対応していますので、日本語化されたものを探さなくても大丈夫です。「Business Edition(64bitのみ)」と「Home Edition(32bit・64bit)」がありますが、今回は「Home Edition」の「SolydX」を選びました。サイトのメニューから「Home Edition → SolydX」と進み、次の画面で右側にある「SolydX 32-bit (1.3G) → Direct」で直接isoファイルをダウンロードできます。遅い場合は「Mirror download」から。 Torrentでも可。ただし「201405 以前の Torrent 使用による入手は法律違反になる可能性が高いため、行わないで下さい。(SolydX / SolydK 日本語情報サイトより引用)」とのことです。
LiveUSB(もしくはLiveCD)の作成
LiveUSBを作るには Unetbootin を使うのがカンタンです(過去記事参照)。
LiveCDなら ImgBurn などを使いましょう。
参考:imgburn 使い方 – Google 検索
USBメモリでなくても「microSD⇔USB変換アダプタ」を使ってLiveUSBを作ることもできます。100円ショップのもので十分です。
ライブ起動

作成したLiveUSB(もしくはLiveCD)からインストールしたいPCを起動します。PCによって異なりますが、BIOS/UEFIの初期画面が表示されているうちに[F2]や[F8][F10][F12]などのファンクション・キーを押していると、ブート・デバイスを選択できます。起動すると上のようにブートローダの画面になります。「↑↓キー」で項目を選択し「Enter」で決定します。
ここから直接OSのインストールはできないようなので、まずはライブ起動します。一番上の「Start SolydX」を選択します。

起動直後のデスクトップ画面です。ここではまだ英語表記になっています。使い方は後述しますが、左下の「Menu」から各種アプリケーションや設定が行えます。画面右下の通知領域から有線・無線LANに接続することができます。予めパスワードを控えておきましょう。
表記が英語のままでも一通り使えるので、まずはPCの環境に合うか試してみましょう。
インストール
デスクトップ画面にある「Install SolydXK(インストーラー)」をダブルクリックか「右クリック → Execute」で実行します。「Menu」からなら「Menu → System → Install SolydXK」でも同じです。

インストーラーの始めの画面で「日本語」が選択できます。これで日本語環境でインストールできます。インストール後の日本語化作業は不要です。

キーボードは「Generic 105-key(Intl)PC」の「Japanese」で大丈夫だと思います。念のため画面下の入力欄でテストしてみて下さい。

ユーザー情報の入力。ユーザー名やパスワード、ホスト名を設定します。インストール後に変更もできます。

インストール先のドライブを選択します。この画像では内蔵HDDがsda、LiveUSBのUSBメモリがsdbとなっています。今回は内蔵HDDにインストールします。別のUSBメモリを使ってそこにインストールすることも可能です。

パーティションの設定です。この画面では内蔵HDDに elementary OS(参考記事)が単一でインストールされています。Windowsならそのような表記になっているでしょう。画面下の「パーティションの編集」をクリックすると「Gparted」というパーティション編集アプリケーションが開くので、それを使って編集します。

今回は単一インストールするのでこのようにしました。他既存OSと共存させる場合、例えばWindowsをsda1、SolydXをsda2、スワップ領域がsda3のように割り当てます。
他OSとのデュアル(マルチ)ブート環境の構築や、Gparted の使い方は以下を参考にして下さい(自サイト含む)▼
・Puppy Linix と Android-x86 をUSBメモリからデュアルブートする方法 | mogi2fruitsどっとねっと
・Puppy Linix と Android-x86 をUSBメモリからデュアルブートする方法 | mogi2fruitsどっとねっと
・「GParted」の使い方 – パソコントラブルと自己解決

パーティション設定の画面に戻り、画面下の「再読み込み」をクリックするとGpartedで編集した内容が反映されます。
今回はルート(/)とホームディレクトリ(/home)は同一パーティションとしました。インストールするパーティション(ここではsda1)を選択し画面下の「次へ」。

オプションの選択です。ブートローダーをインストールするかどうか、スプラッシュ画面を表示させるかどうか、マルチメディア関連コーデックをインストールするかどうかを選択できます。ブートローダーをインストールした場合はたぶん既存OS(特にWindowsなど)は認識してくれると思いますが・・・(未検証)
後から GRUB2 編集ができるなら必ずしもここでインストールする必要はありませんが、その知識が必要となります。
参考:grub2 設定 – Google 検索

インストール設定の確認。大丈夫なら画面下の「インストール」で開始します。

インストール完了。再起動時にUSBメモリを抜いて下さい。もしくは内蔵HDDから起動です。
使い方・設定など
インストール直後にやること

とりあえずシステムのアップデートをしましょう。デスクトップ画面右下の通知領域からか、もしくは「Menu → システム → アップデートマネージャー」です。「アップデートマネージャー」そのもののアップデートから始まります。
日本語入力環境

インプットメソッドにFcitx、日本語入力システムにMozc(Google日本語入力のオープンソース版)を採用しているので、変換能力は優れています。
アプリケーション
ブラウザは「FireFox」、メーラーは「Thunderbird」、動画再生は「VLC」、音楽再生は「Exaile」、テキストエディタは「Mousepad」、画像編集に「Gimp」、ウィルススキャナーに「ClamTk」…etc
SambaやJavaも導入済みで、そのままフルPCとして使えます。
パッケージインストーラーには「Synaptic パッケージマネージャ」があるので、欲しいアプリケーションがあればここからインストールできます。またネットからダウンロードしたdebファイル(Windowsで言えば.exeや.msiみたいなもの)は「Gdebi パッケージインストーラー」が使えます。
Chromeブラウザ(公式)をインストールしたければこちらからdebファイルをダウンロード、インストールして下さい ▼
・Chrome ブラウザ
LinuxからアクセスすればLinux用の案内が出ています。32bitか64bitか、PCに合ったものを選んで下さい。32bitなら google-chrome-stable_current_i386.deb がファイル名となります。

アプリをショートカットキーで起動する必要もなさそうです。「Menu」は「Windowsキー(SuperKey)」で開くことができるので、そこから「お気に入り」によく使うアプリを入れておけばキーボードだけで起動できます。登録の仕方は「Menu」から該当のアプリを表示させ「右クリック → お気に入りに追加」です。同じ手順で削除も可。
外観の設定

「LightDM Manager」「ウィンドウマネージャー」「外観」などで変更できます。「Debian Plymouth Manager」で起動画面もカスタマイズ可能です。
あとがき:使用感・メモリ使用量など
何もカスタマイズする必要がないので、むしろつまらないくらいです(褒め言葉)。
冒頭でも書きましたがWindowsXP機だと若干もたつく可能性はあります。今回試した環境ではCPU1.66GHz(Atom N455)、メモリ2GBですが、特に不便なく使えました。メモリ使用量は初期状態だと300~400MBくらい。Chromeブラウザを使用して400~600MBくらいです。
WindowsXP機ならもっと軽い Puppy Linux とかUbuntuベースの linuxBean や elementary OS、スマホやタブレットでAndroidに慣れているなら Android-x86 なんかの方が軽快に使えるかもしれませんね。少なくともUbuntuデフォルトよりは軽いですが。
日本語環境の構築やアプリの導入など、インストール後の設定を何もしなくても何不自由無く使えるトコロが最大の利点と言えそうです。